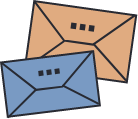


キャリア支援の必要性が高まる中で、企業からは「管理職がキャリア面談に消極的」「何を話せばよいか分からない」「評価面談と混同されている」といった声が多く寄せられています。
背景には、「対話の目的があいまい」「管理職の役割認識が不明確」「人事制度との連動性の欠如」など、制度設計と運用の両面での課題が存在します。特に評価制度との混同により、「答えを出す場」と誤解されてしまい、内省の時間として機能していないケースも見受けられます。
本記事では、企業の人事・育成担当者向けに開催したQ&Aセッションセミナーから、実際に多くの方が悩んでいた7つの質問と、現場で活かせる実践的なアドバイスを厳選してご紹介します。
まずは、キャリア支援の目的を「部下の成長支援」というよりも「マネジメントをしやすくする手段」と捉えてもらうことが鍵です。キャリア面談を通じて部下の価値観や強みを知ることで、業務のアサインやコミュニケーションが円滑になり、結果的に上司自身の負担が軽減されるケースも多く見られます。
また、当社では「マネジメントの引き出しを増やす感覚で取り組む」ことを提案しています。キャリア支援は「特別な支援」ではなく、「日常のマネジメントの一部」として捉えてもらうと、管理職も前向きに関わりやすくなります。
キャリア面談においては「Will・Can・Must」の3つの視点を取り入れることをお勧めします。
 この3点について本人の口から語ってもらい、最後に上司からの期待や成長機会についてすり合わせを行うことで、部下の内省と納得を促進できます。
この3点について本人の口から語ってもらい、最後に上司からの期待や成長機会についてすり合わせを行うことで、部下の内省と納得を促進できます。
「何を話せばいいか分からない」という管理職には、テンプレートやフレームワークを共有することで、安心感を持って面談に臨んでもらうことができます。以下より無料でダウンロードいただけます。
キャリア面談にすぐ使える「WILL・CAN・MUST記入シート」(ダウンロード)※クリックすると、パワーポイントがダウンロードされます。
はい、別に設けることを強く推奨します。
評価面談は業績・成果に対するフィードバックの場であり、キャリア面談は本人の将来像や価値観を引き出すための「対話の場」です。目的が異なるため、同じ面談で扱うと部下は「どう話しても評価に影響するのでは」と感じ、本音が出にくくなります。
キャリア面談の本来の目的は、内省と方向づけ。安心して話せる場をつくるためにも、制度設計上の分離だけでなく、実施時の上司側の意識づけも重要です。
キャリア面談では、上司は「助言者」ではなく「聴き手」のスタンスが基本です。
ありがちな失敗が、「自分のキャリアを語って聞かせてしまう」「無意識に成功体験を押しつけてしまう」といったもの。こうした一方通行の対話は、部下の自己開示を妨げ、面談の意味を損ないます。
当社では、面談に臨む上司向けに「上司がまず把握すべき、キャリア面談の基本を学ぶ」実践的なトレーニングを提供しています。動画での良い例・悪い例を通じて、理解しやすい構成が好評です。
無理に「成長意欲」を引き出そうとするのではなく、相手の関心領域や価値観に寄り添った対話から始めるのがポイントです。
年上部下との面談では、「人生の整理」や「気になっていることの棚卸し」を手助けするつもりで関わると、相手も話しやすくなります。部下本人がどう働きたいかを大切にする姿勢が、信頼関係構築の第一歩となります。
当社では、年上部下との信頼構築に特化したドラマ型eラーニングや支援ツールも用意しており、多くの企業様で対話のきっかけ作りに活用されています。
理想は四半期に1回、1時間の面談を組むことで、関係性の質を高めることができます。
1時間面談の構成例
このような配分にすることで、部下にとっても「話すことが目的の面談」として、より本音を語りやすくなります。
価値観や人生観を探るうえで、プライベートに関連する話題に触れるのは自然なことです。
ただし、「何でも聞いていい」ではなく、「相手が話したくないことは聞かない」というスタンスが大切です。面談の冒頭で「無理に話す必要はありません」と一言添えるだけで、部下の安心感が高まり、結果的に深い話も引き出せることがあります。
当社では「安心して話せる場づくり」に必要な対話の工夫も、具体例を交えて解説したハンドブックの作成をしております。
キャリア支援を本質的に機能させるには、制度整備に加えて、日常の対話を通じた「関係の質」の向上が不可欠です。
特に制度を設計・運用する人事部門にとっては、管理職が適切に対話を担えなければ、せっかく整えたキャリア支援制度も形骸化してしまうリスクがあります。現場の上司が機能して初めて、社員のキャリア自律を支える仕組みとして実効性が生まれます。
また、こうしたキャリア支援は、単に「個人のキャリア開発」にとどまらず、社員一人ひとりのモチベーションやエンゲージメントの向上、さらには組織全体の生産性や創造性の向上にも直結します。社員が自身の将来に納得し、主体的に働ける環境を整えることは、企業にとって持続的成長の基盤となる重要な経営課題でもあります。
私たちは、研修・制度設計・上司向け支援などを通じて、単発的な取り組みで終わらせず、現場に根づく支援の仕組みづくりをサポートしています。
本記事のもととなった、キャリア支援における「管理職の関わり方」に関するQ&Aセッションの録画を公開中です。
