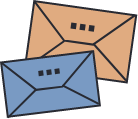


「最近、Aさんの勤務態度が気になっています。遅刻や欠勤が増えていて、指示を聞いていないこともあるようです。」管理職からこのような相談を受けることは、人事の現場では珍しくありません。
ただし、こうした状況に対してすぐに厳しい対応を取るのは適切ではありません。
業務パフォーマンスや職場での振る舞いに課題が見られる社員に対しては、本人の状況を正しく理解し、改善に向けた支援を行うことが重要です。
一方で、適切な対応をしないまま問題を放置すると、職場の士気や生産性の低下につながる可能性があります。
本記事では、問題社員対応の基本的な考え方と、適切なプロセスについて解説します。
「特定の社員が問題行動を起こしているが、どう対応するべきかわからない...」
そのまま対応を先送りにしてしまうと、職場には次のような影響が出る可能性があります。
問題が長引けば、チーム全体に悪影響が広がります。
だからこそ、人事担当者は「適切な対話」と「サポート」を通じて、問題のある社員と向き合うことが大切なのです。
問題社員の対応においては、「本人の成長を促し、組織としての健全な環境を維持する」という視点が欠かせません。また、業務パフォーマンスや勤務態度の問題が見られる社員であっても、その背景には環境の変化や職場との相性、本人が抱えている悩みやストレスが影響している可能性があります。単に「スキル不足」や「適性の問題」と決めつけず、マインド面での影響も含めて理解し、適切なサポートを行うことが大切です。
ただし、感情的な対応になったり、急ぎすぎたりすると、本人が納得しないまま関係が悪化してしまうこともあります。対応を進める際には、次のようなポイントを意識することが大切です。
「最近、態度が悪い」「仕事の進捗が遅い」といった漠然とした印象だけで判断せず、具体的な事実を整理しましょう。
例えば、遅刻や欠勤の頻度、業務の進捗への影響、他の社員との関係性などを客観的に確認することが重要です。また、本人にヒアリングを行い、課題の背景に何があるのかを丁寧に聞くことも必要です。
改善を求める場合、「どう変わるべきか」が本人に伝わっていなければ、適切な行動につながりません。
期待される役割や求められる行動について、具体的な指摘を交えながら対話を進めることが大切です。
× 「最近、仕事に対する姿勢がよくないね」
〇 「ここ1カ月間で遅刻が5回ありました。この状況が続くと、業務に支障が出るため、改善していきましょう」
このように、具体的な事実を示しながら伝えることで、本人も状況を理解しやすくなります。
指摘するだけでなく、改善をサポートする仕組みを整えることも大切です。
例えば、業務スキルに課題がある場合はトレーニングや研修を実施する、勤務態度に問題がある場合は具体的な改善目標を設定し、進捗を確認するなどの対応が考えられます。
このようなプロセスを通じて、本人が成長できる環境を提供することが、人事の役割のひとつです。
ミスマッチ社員への具体的な対応方法については、こちらのセミナーでも詳しく解説しています。
「どうする!?ミスマッチ・不活性人材」無料録画セミナー
(例:遅刻や欠勤が多い、業務への取り組みが消極的、指示を無視する)
職場でのルールや基本的な業務姿勢に問題がある社員に対しては、単に「注意する」だけではなく、何が問題なのかを明確に伝え、改善のためのサポートを行うことが重要です。
また、本人が気づかぬうちに、周囲に悪影響を与えているケースもあるため、具体的なフィードバックを行い、意識改革を促すことが必要です。
(例:期待される成果を出せていない、業務ミスが多い、スキル不足が見られる)
期待される成果を出せていない社員に対しては、単なる「努力不足」と決めつけず、スキルや適性を慎重に見極めることが重要です。業務内容が本人のスキルに合っていない場合、適切なトレーニングや配置転換を検討する必要があります。
低迷が続く場合は、PIP(業績改善プログラム)を導入し、明確な改善目標を設定する方法もあります。
PIP(業績改善プログラム)を詳しく解説した記事も合わせてご覧ください
(例:周囲とトラブルが多い、協調性に欠ける、コミュニケーションに課題がある)
職場の雰囲気を悪化させる社員は、業務スキルに問題がない場合でも、チーム全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。周囲とトラブルが多い、協調性に欠ける、コミュニケーションがうまくいかない...。
こうした社員の対応を誤ると、チームの生産性や職場の心理的安全性が損なわれてしまう可能性があります。
このような社員に対しては、単に注意するのではなく、どのような行動が求められているのかを具体的に伝えることが重要です。
特に、問題社員への対応スキルが求められるのは管理職です。
耳に痛いことも恐れずに適切なフィードバックをし、指導を行うために、管理職向けのトレーニングを活用することも検討しましょう。
管理職向けネガティブフィードバック研修の詳細はこちら(ダウンロード)
(例:企業文化や業務内容に適応できず、モチベーションが低下している)
企業文化や業務環境に適応できない社員がいると、本人のモチベーションが低下し、最終的にパフォーマンスの低下につながることがあります。
特に、新しい組織風土や業務プロセスに馴染めないケースでは、早期の対話と支援が重要になります。単に「努力不足」と片付けず、本人が何に違和感を感じているのかをヒアリングし、適応をサポートすることが必要です。場合によっては、配置転換やキャリアの見直しを検討することも選択肢になります。
早期退職優遇制度について、分かりやすく解説した記事も合わせてご覧ください。
早期退職優遇制度とは?優遇措置の種類や導入までの流れを分かりやすく解説!
(例:部下の指導ができない、意思決定が遅い、チームマネジメントに課題がある)
管理職が適切にマネジメントできていないと、部下の成長が妨げられ、組織全体の生産性が低下します。特に、指導力不足や意思決定の遅さは、チーム全体に悪影響を及ぼすため、早めの対応が必要です。
管理職が身につけるべきスキルや役割については、以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。
管理職研修はどんな内容を実施すべき?管理職に求められる役割と合わせて解説!
問題社員の対応は、人事にとって難しい課題ですが、適切なプロセスを踏むことで、本人の成長を促し、職場全体の生産性を守ることができます。問題社員への対応は、「辞めさせること」を目的にするのではなく、職場の健全化と、本人の成長を促すためのプロセスです。しかし、本人が現職での適応が難しい場合や、企業の戦略的な判断として別のキャリアを提案する場合には、円滑な転職支援が求められます。その際、再就職支援サービスを活用することで、企業側のリスクを最小限にしつつ、本人が納得できるキャリア移行をサポートできます。
再就職支援サービスのメリットや正しい活用方法は、以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。今知っておくべき「再就職支援」。メリットや正しい活用方法とは?
問題社員対応にお悩みの方は、ぜひ弊社のコンサルティングサービスをご活用ください。貴社の課題に合わせた最適な支援をご提供します。
